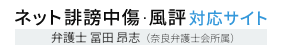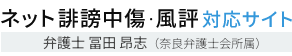当ページでは、インターネット上の投稿に対する発信者情報開示請求(投稿者の特定)について詳しく解説します。
発信者情報開示請求については、プロバイダのログの保存期間が限られているため、迅速な対応が重要となります。
お悩みになる前にご相談いただいた方がより良い解決につながる場合があります。
是非お気軽にお問い合わせください。
また、インターネット上の誹謗中傷や風評被害にお悩みの方向けに、発信者情報開示請求(投稿者の特定)を含む被害者向けサービスの全体像をお示ししたページをご用意していますので、併せてご参照ください。
インターネット上の誹謗中傷・風評被害を受けられた被害者向けサービスはこちら
目次
投稿者の特定について
インターネット上の誹謗中傷・風評投稿の多くは匿名なので、通常、投稿者が誰なのかはわかりません。
もっとも、投稿者につながる情報(発信者情報)は、プロバイダが保有している可能性があります。
コンテンツプロバイダ(投稿先のサイト管理者)は、投稿に関する情報(IPアドレスなど)や、投稿したアカウントの情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)を持っている可能性があります。
アクセスプロバイダ(投稿の通信が経由した通信網を持つプロバイダ)は、投稿時のIPアドレスを使用した契約者情報(氏名、住所など)を特定できる可能性があります。
このため、投稿者の特定は、プロバイダに対する発信者情報開示請求を軸に行います。
当ページでは、どのような投稿であれば削除請求が認められるのか、投稿者特定の流れ、発信者情報開示請求の方法などを説明します。
どのような投稿であれば発信者情報開示請求が認められる可能性があるのか?
当然ですが、どのような投稿でも発信者情報開示請求が認められるわけではなく、投稿が「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」であること、投稿の「流通によって権利が侵害されたことが明らか」であることが必要です(プロバイダ責任制限法5条1項、2条1号)。
①「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」とは、要するに、不特定の者が閲覧できるSNSや掲示板などにおける投稿をいいます。このため、メールやDMなど1対1の通信は、この要件を満たさず、発信者情報開示請求ができません。
②どのような投稿が、「流通によって権利が侵害されたことが明らか」といえるのかについて、別ページにて説明していますので、ご参照ください。
どのような投稿であれば削除・開示が認められる可能性があるか?についてはこちら
投稿者の特定の流れ
投稿者の特定は、インターネット上の投稿の通信を遡って行います。
インターネット上の投稿の通信の基本的な流れは、かなりシンプルに表現すると、以下のようになります。
投稿者の端末
↓
アクセスプロバイダ
↓
サイトのサーバー(コンテンツプロバイダ)
被害者の立場からすると投稿されたサイトだけが手がかりなので、投稿者の特定は、コンテンツプロバイダへの発信者情報開示請求から始まり、通信とは逆の流れで特定します。
サイトによってコンテンツプロバイダの保有しうる発信者情報が異なるため、いくつかの特定パターンがあります。
パターンによっては時間制限が厳しいため、適切なパターンの選択や請求を迅速に行う必要があります。
なお、複数のパターンを併用する場合もあります。
パターン①:氏名・住所を登録する会員サイトの場合
サイト管理者(コンテンツプロバイダ)に対し、氏名・住所の発信者情報開示請求をします。裁判外の請求では、投稿者が同意しない限り、開示される可能性が低いので、基本的には裁判上の請求(訴訟又は非訟)を行います。
パターン②:電話番号・メールアドレスを登録する会員サイトの場合
サイト管理者(コンテンツプロバイダ)に対し、電話番号・メールアドレスの発信者情報開示請求をします。裁判外の請求では、投稿者が同意しない限り、開示される可能性が低いので、基本的には裁判上の請求を行います。
電話番号・メールアドレスが開示されたら、弁護士会照会という弁護士法上の手段を利用して、電話番号・メールアドレスの契約者の個人情報の開示を試みます。
パターン③:投稿から時間が経過していない場合
コンテンツプロバイダに対し、IPアドレスなどの開示請求を行い(第1段階)、開示された情報を基に、投稿者が契約しているアクセスプロバイダを特定し、そのアクセスプロバイダに対し、投稿者の契約者情報の開示を請求します(第2段階)。
このパターンは、アクセスプロバイダにログが残っている場合にのみ成功するため、アクセスプロバイダのログ保存期間内に間に合うかどうかがポイントとなります。ログ保存期間は、アクセスプロバイダによって異なりますが、投稿から3か月程度が多い印象です(3カ月より長いアクセスプロバイダもあるようです)。
第1段階(コンテンツプロバイダ)
サイト管理者(コンテンツプロバイダ)に対し、投稿に関する情報(IPアドレスなど)の発信者情報開示請求をします。この場合は、プロバイダによっては裁判外の請求に応じる可能性があるので、裁判外の請求も検討します。
第2段階(アクセスプロバイダ)
IPアドレスから投稿の通信を経由したアクセスプロバイダを特定し、アクセスプロバイダに対して、契約者情報の発信者情報開示請求をします。
裁判外の請求では、投稿者が同意しない限り、開示される可能性が低いので、基本的には裁判上の請求を行います。
投稿からの経過時間によっては、裁判上の請求の前に、ログ保存の依頼などを検討します。
なお、投稿者が格安SIMを利用していた場合、通信に複数のアクセスプロバイダが順次関わっているため、それぞれのアクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行う必要があります。
発信者情報開示命令申立(非訟手続)について
2022年10月から、発信者情報開示命令申立(非訟手続)が始まりました。この手続きを利用することで第1段階と第2段階をまとめて行うことができる場合があります。
ただし、これは、プロバイダが手続きに協力しないと成り立たない制度であり、非協力的なプロバイダ相手では利用できません。
発信者情報開示請求の方法
発信者情報開示請求の方法は、大きく分けて、裁判外の開示請求(任意の開示請求)と裁判上の開示請求の2種類があります。
裁判外の開示請求
裁判外の開示請求は、サイト管理者に直接発信者情報開示を求めるものです。
開示するかどうかの判断をするのはサイト管理者です。
裁判外の請求にあたっては、プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト(※)にて公表されている「発信者情報開示請求書」をプロバイダに郵送して請求します。サイトによって、アレンジした発信者情報開示請求書を用意していることがあり、また、発信者情報開示請求書に添付する書類の指定内容が異なるため、注意が必要です。
発信者情報開示請求書の郵送後、プロバイダは、投稿者と連絡が取ることができる場合は、投稿者に対し、開示に同意するかどうか意見を聴きます。
プロバイダは、発信者情報開示請求書、添付資料、投稿者の意見等から、開示するかどうかを判断します。
ただし、サイトにもよりますが、裁判外の請求で開示されることは少ないでしょう。サイト管理者が発信者情報開示の要件判断を誤って開示した場合、犯罪になりうるなど、開示のリスクの方が大きいからです。
所要期間は、基本的に2週間~4週間ほどのようです。
裁判上の開示請求
裁判上の発信者情報開示請求は、裁判所に訴状や申立書を提出するものです。
開示するかどうかの判断をするのは裁判所です。
裁判所が中立的な立場から判断します。
裁判外の請求は、さらに仮処分手続、非訟手続、訴訟手続の3つに分けられます。
開示仮処分
仮処分とは、民事保全法で定められた裁判所の命令です。
「仮」という名のとおり、本来は、その後本案訴訟(公開の裁判)で最終的な結果が出るまでの暫定的な命令です。
ただ、実務上、開示仮処分では、プロバイダは仮処分に従って発信者情報の開示を行ない、仮処分が出た後の本案訴訟(開示訴訟)に至らないのが通常です。
特徴は以下のとおりです。
- 手続の進行が迅速
- 手続が非公開
- 手続上、立証の程度が疏明(一応確からしいという推測を得させる程度の挙証)で良い
- 開示請求を多く扱う裁判所の担当が期待できる
- 執行の申立てが迅速にできる
- 「生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため」という要件により、開示を求めることができる情報がアクセスプロバイダの特定に必要な情報(IPアドレスなど)のみ
- 仮処分命令発令のために担保金(10万円~)を供託する必要がある
開示を求めることができる情報に限定があるため、仮処分が利用できるのは、パターン③の第1段階のみです。
なお、パターン③においても、第1段階と第2段階をまとめて非訟手続でできる場合は非訟手続を選択するのがベターです。
このため、仮処分手続を利用するのは、パターン③かつサイト管理者が非訟手続に非協力的なコンテンツプロバイダの場合となります。
所要期間は、基本的に2週間から3ヶ月ほどです。
非訟手続
非訟手続(発信者情報開示命令申立)は、2022年10月に始まった比較的新しい手続です。
特徴は以下のとおりです。
- 手続の進行が仮処分と比べると遅め(訴訟より早い)
- 手続が非公開
- 手続上、立証の程度が証明(通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を得させる程度の挙証)まで必要
- 開示請求を多く扱う裁判所の担当が期待できる
- 決定があってもしばらく執行の申立てができない
- 開示を求めることができる情報は、法令で定められたもの全て
非訟手続では、サイト管理者によっては、パターン③の第1段階と第2段階をまとめて行うことができる場合があります。
また、仮処分と異なり、開示を求めることができる情報は、法令で定められたもの全てなので、パターン①、パターン②でも利用できます。
所要期間は、1か月から3か月、場合によっては数か月かかることもあります。
開示訴訟
開示訴訟は、通常の民事訴訟で開示判決の獲得を目指すものです。
特徴は、以下のとおりです。
- 手続の進行が比較的遅い
- 手続が公開(例えば、原則として、裁判記録は誰でも閲覧可能です。)
- 手続上、立証の程度が証明(通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を得させる程度の挙証)まで必要
- 開示請求に慣れた裁判所へ配点されるとは限らない
- 判決があってもしばらく執行の申立てができない
- 開示を求めることができる情報は、法令で定められたもの全て
非訟手続の方が、手続が比較的迅速、手続が非公開というメリットがある一方で、開示訴訟のメリットは乏しいため、非訟手続を利用することがほとんどです。
所要期間は、基本的に半年から場合によっては1年以上かかることもあります。
手続比較表
| 迅速性 | 公開の有無 | 立証の程度 | 担当裁判所 | 執行の迅速性 | 請求可能情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裁判外開示 | 〇 | ※ | ※ | - | 執行不可 | 法定の情報全て |
| 開示仮処分 | 〇 | 非公開 | 疎明 | 〇 | 〇 | 一部のみ |
| 非訟手続 | △ | 非公開 | 証明 | 〇 | × | 法定の情報全て |
| 開示訴訟 | × | 公開 | 証明 | △ | △ | 法定の情報全て |
※プロバイダ次第
削除請求もお考えの場合
削除については、投稿者の特定(発信者情報開示請求)・投稿者への損害賠償請求をお考えの場合、最低限、投稿の証拠化を済ませてから請求しなければなりません。
発信者情報開示請求では、請求者側で証拠を添付のうえ、投稿を特定しなければならないからです。
プロバイダ責任制限法の改正の影響
2024年5月17日、プロバイダ責任制限法の改正法である情報流通プラットフォーム対処法が公布されました(実際に施行されるのは、2024年5月17日から1年以内です)。
しかし、改正事項は削除に関するものなので、開示請求に関しては影響がありません。
「投稿者の特定は必ず成功しますか?」というご質問について
よくある質問の「投稿者の特定は必ず成功しますか?」をご参照ください。
「投稿者特定→慰謝料等請求にはどのようなリスクがありますか?」というご質問について
よくある質問の「投稿者特定→慰謝料等請求にはどのようなリスクがありますか?」をご参照ください。
お気軽にお問い合わせください。
投稿者特定については、用意されている手続や採り得るパターンが多く複雑です。
また、迅速な対応をすることで投稿者特定の可能性が上がる場合があります。
このため、お悩みになる前にご相談いただいた方がより良い解決につながる場合があります。
是非お気軽にお問い合わせください。