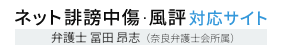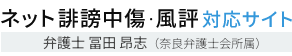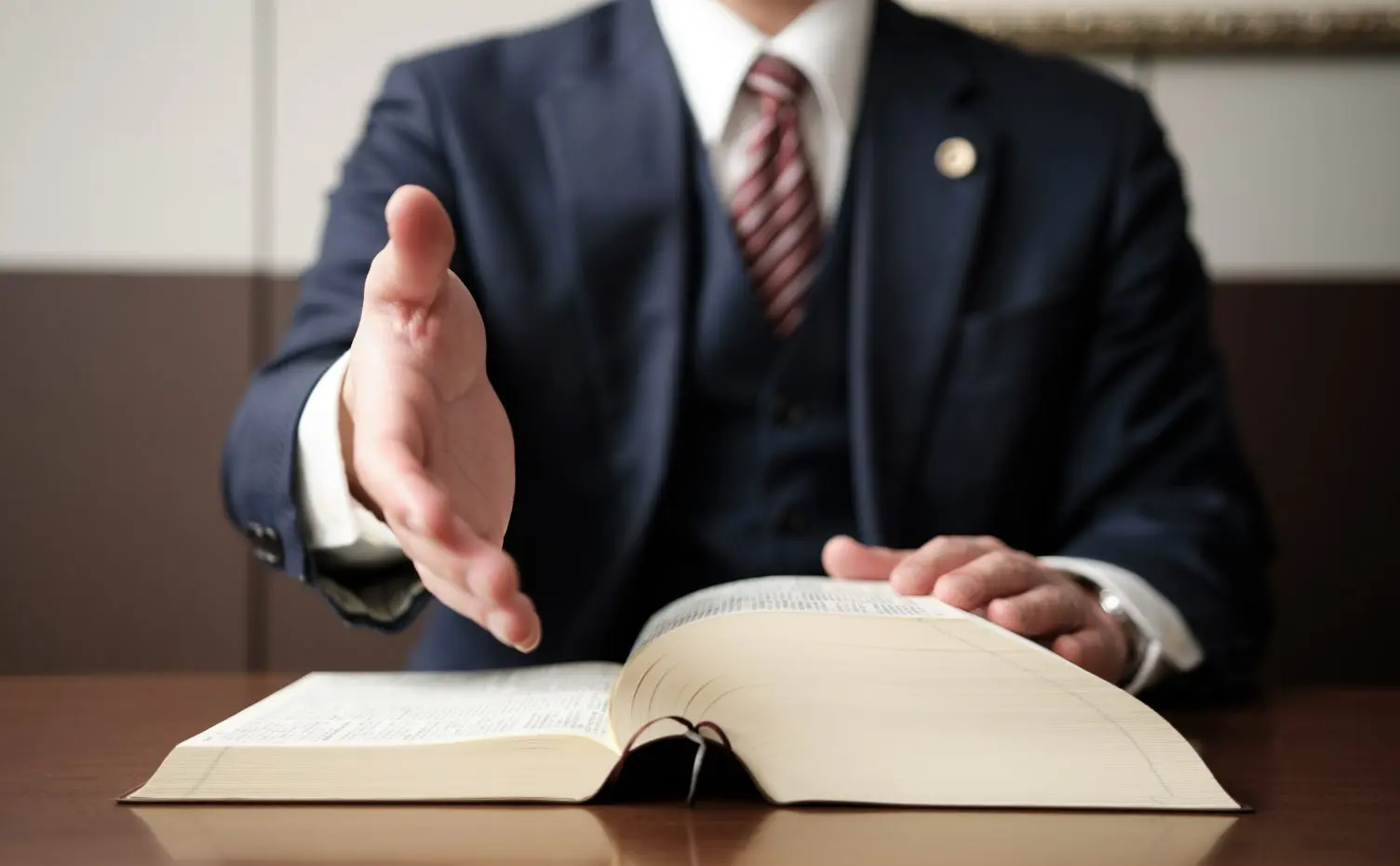当ページでは、インターネット上の投稿について慰謝料等請求を受けた場合の対応について説明します。
慰謝料等請求を受けたのに長期間放置してしまうと、裁判外であれば負担の大きい裁判になってしまう可能性が高くなり、裁判上であれば請求額に近い金額が認められる可能性が高くなってしまいます。
このため、迅速な対応が重要となります。
お悩みになる前にご相談いただいた方がより良い解決につながる場合があります。
是非お気軽にお問い合わせください。
また、意見照会(開示請求)・慰謝料等請求を受けた方(投稿者)向けに、投稿者向けサービスの全体像をお示ししたページをご用意していますので、併せてご参照ください。
意見照会(開示請求)・慰謝料請求を受けた方(投稿者)向けサービスはこちら
目次
慰謝料等請求について
「何が起こっているのか」「これからどうなるのか」などについては、以下のリンクで詳しく解説していますので、ご参照ください。
意見照会(開示請求)・慰謝料請求を受けた方(投稿者)向けサービスはこちら
当ページでは、慰謝料請求を受けた場合の具体的な対応について説明します。
裁判外の請求について
請求者側は、特定のインターネット上の投稿について、発信者情報開示請求などによる特定を経て、慰謝料等を請求しています。
すなわち、特定の投稿に関しては、裁判所(又はプロバイダ)によって、「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかである」という判断がされているということになります。
慰謝料等の請求に対しては、この点を踏まえて、慎重に対応する必要があります。
裁判外の請求が届いたら確認すること
裁判外の請求が届いたからといって、請求内容が妥当なものであるとは限りません。
投稿者側に有利な事情がないか、請求書の内容を慎重に確認する必要があります。
対象投稿
慰謝料等請求の原因となっている投稿を確認します。
プロバイダに対し、意見照会の回答を行っている場合は、意見照会の対象投稿と照合します。
意見照会の対象投稿のみが挙げられている場合は、意見照会の回答内容を踏まえても、権利侵害が「明らか」と判断されたことがわかります。この場合であっても、権利侵害を争う余地がないとはいえませんが、比較的小さいといえます。
逆に、意見照会の対象投稿以外の投稿も挙げられている場合は、この投稿に関しては、少なくとも投稿者側の言い分を踏まえて権利侵害が「明らか」と判断されているわけではなく、権利侵害を争う余地が比較的大きい可能性があります。
なお、対象投稿が特定されていない場合は、請求者側に特定を求めることを検討します。
請求金額と支払可能額
請求者側が求める金額を確認します。
必ずしも請求金額どおり支払わなければならないものではありません。
ただ、交渉のため、財産状況に照らし、これ以上は支払えないというライン(支払可能な上限金額)を確認し、請求金額との乖離を把握することが重要となります。
必要に応じ、請求者側に支払可能額を説明できるようにしておきましょう。
回答期限
請求書に記載された回答期限を確認します。
回答期限が過ぎたからといって即訴訟になるとか、交渉の余地が全くなくなるという事態になることは少ないと思われますが、スムーズな交渉のため、回答期限を意識する必要があります。
慰謝料等の相場は?
慰謝料等の金額に関する交渉は、最終的に判決に至った場合に認められ得る額を念頭に置いて行います。
もっとも、裁判例から、最終的に判決に至った場合に認められ得る額を詳細に予想するのは難しく、かなり概括的な予想にならざるを得ません。
判決では投稿内容をはじめ様々な事情が考慮されており、全く同じ事情の事件は想定し辛いからです。
このため、慰謝料等の相場を明示するのは難しいですが、裁判例の傾向としては、例えば、名誉権を侵害する投稿が原因で認められた慰謝料等の金額は、裁判例からすると100万円以上は少なく、50万円以下が多い印象です。
これとは別に、弁護士費用や投稿者の特定にかかった弁護士費用が加算される場合がありますが、投稿者の特定にかかった弁護士費用については、裁判所の判断が分かれており、慰謝料以上に予想が難しいです。
慰謝料等を支払う余裕がない場合は?
慰謝料等を支払う余裕がない場合は、これを前提に交渉することとなります。請求者側にとっても、ない袖は振れないことを承知しているため、投稿者側の支払能力を考慮せざるを得ないからです。
ただし、請求者側、投稿者側の言い分をそのまま信用してくれるとは限りません。このため、必要に応じ、財産状況の根拠資料を開示することも検討します。
支払能力を理由に金銭面を譲歩してもらえる場合、他の条件(謝罪文の交付や、二度と同様の投稿を行わない約束や、同様の投稿をした場合の違約金など)の要望がされることがあり、検討することとなります。
交渉について
確認した結果(投稿内容、支払能力、裁判例など)だけでなく、裁判になった場合の双方の負担も考慮したうえで、請求者側と条件を協議することとなります。
条件が決まったら、示談書を作成します。
裁判上の請求について
裁判上の請求(訴状)が届いたら確認すること
裁判外の請求と同様です。
裁判上の請求の場合は、裁判所に対する答弁書の提出期限が定められています。
提出期限を過ぎたからといって答弁書提出不可になるわけではありませんが、遅くとも、第1回口頭弁論期日の前日までには提出するのが無難です。
なお、期日に出席せず、答弁書も提出しなかった場合は、請求額全額またはこれに近い金額が認容され、強制執行されるおそれがあるので注意が必要です。
反論の検討
慰謝料等請求は、民法709条、710条に定められた、一般的な不法行為に基づく請求です。
請求の要件は、民法709条によると以下のとおりです。
- 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」したこと
- 「損害」が「生じた」こと、
- ①と②の因果関係
これらの要件それぞれについて、反論をすることになります。
権利侵害についての反論(①)
意見照会の対象投稿が挙げられている場合は、意見照会の回答内容を踏まえても、権利侵害が「明らか」と判断されているため、見通しとしては厳しいと言わざるを得ないです。
しかし、慰謝料等請求の担当裁判官が、発信者情報開示請求の担当裁判官と同じ可能性はかなり低く、発信者情報開示請求の判断に法律上拘束されないため、意見照会の回答内容も含めて反論をすべきです。
また、慰謝料請求では、発信者情報開示請求とは異なり、「故意又は過失」も要件となるため、発信者情報開示請求では有効でなかった反論が可能です。例えば、名誉権侵害が主張されている場合に、「真実だと勘違いしても仕方のない状況だった」などと「故意又は過失」を否定する反論が有効になる場合があります。
損害(因果関係)についての反論(②、③)
投稿によって売上が減少したことや、キャンセルが相次いだことなどを理由に、本来得られた利益分を請求されている場合は、投稿との因果関係がないことを反論します。
具体的な算定ができない損害(個人の場合は「慰謝料」、法人の場合は「無形の損害」と呼ばれています。)については、類似事例の裁判例を挙げながら、高額すぎるなどと反論します。
和解の打診
訴訟が進行する中で、裁判官から、具体的な金額を提示して、和解を勧められることがあります。
この金額は、裁判官の、その時点での心証を前提にしています。
また、裁判外の請求と同様、支払能力などを考慮した柔軟な条件を設定できます。
和解をせずに判決に進むよりも早期解決ができるというメリットもあります。
このため、基本的には、検討してもよいと思われます。
お気軽にお問い合わせください
慰謝料等請求については早期の状況確認と方針検討が重要です。
お悩みになる前にご相談いただいた方がより良い解決につながる場合があります。
是非お気軽にお問い合わせください。