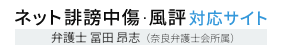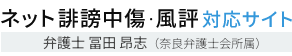当ページでは、プロバイダが、インターネット上の投稿に関し、損害賠償請求を受けた場合の対応について説明します。
プロバイダとしては、損害賠償請求に対し、プロバイダ責任制限法上の免責規定を前提に対応する必要があります。
プロバイダ向けサービスの全体像をお示ししたページもご用意していますので、併せてご参照ください。
プロバイダに対する損害賠償請求の種類
インターネット上の投稿についてプロバイダが受け得る損害賠償請求には、大きく分けて、削除に関する損害賠償請求と発信者情報開示に関する損害賠償請求があります。
削除に関する損害賠償請求は、問題とされている投稿に対する削除権限があることが前提の請求であり、基本的にSNSやブログなどのサイト管理者やプラットフォーム事業者であるコンテンツプロバイダ特有の請求です。
発信者情報開示に関する損害賠償請求は、コンテンツプロバイダに限らず、発信者情報開示請求を受け得るアクセスプロバイダも請求される可能性があります。
以下、それぞれ説明します。
削除に関する損害賠償請求について
削除に関する損害賠償請求については、投稿を問題視する削除請求者側からの投稿を削除しなかったことに対する損害賠償請求と、投稿者からの投稿を削除したことに対する損害賠償請求の2種類が考えられます。
プロバイダとしては、投稿を削除してもしなくても、これらのうちいずれかの損害賠償請求を受けるリスクがあります。
ただし、いずれについてもプロバイダ責任制限法上の免責規定があるため、プロバイダが過度に責任を負わない制度になっています。
このため、損害賠償請求を受けても、これらの免責規定に照らして正確にリスクを検討する必要があります。
以下、それぞれ、免責規定を中心に説明します
投稿を削除しなかったことに対する損害賠償請求
投稿を削除しなかったことに対する損害賠償請求は、民法709条、710条に定められた、一般的な不法行為に基づく請求です。
このため、プロバイダは、不法行為に基づく損害賠償請求の民法上の要件を満たさなければ、損害賠償義務を負いません。
さらに、プロバイダ責任制限法3条1項は、プロバイダが損害賠償義務を負う場合を2つの場合に限定し、これら以外の場合については(つまり、原則として)免責すると定めています。
不法行為に基づく損害賠償請求の民法上の要件
民法709条によると、
- 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」したこと
- 「損害」が「生じた」こと、
- ①と②の因果関係
が要件となります。なお、これらの要件を満たした場合であっても、損害賠償義務を負わない場合があります(正当防衛など)。
プロバイダとしては、投稿が他人の権利を侵害しないこと、投稿を削除しないのもやむを得なかったこと(いずれも①)、請求者側に投稿と因果関係のある損害が発生していないこと(②③)などの反論要素があります。
プロバイダ責任制限法3条1項の免責要件
プロバイダ責任制限法3条1項によれば、以下の2つのいずれかを満たさない限り、(つまり原則として)プロバイダは免責されます。なお、細かい要件は他にもありますが、問題にならないことが多いため、ここでは割愛します。
- プロバイダが、情報(対象投稿)の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき
- プロバイダが、情報(対象投稿)の流通を知っていた場合で、かつ、情報(対象投稿)の流通によって他人の権利が侵害されていること知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき
逆にいうと、Ⅰ又はⅡの場合は、他の要件を満たせば責任を負うということになります。
Ⅰについて
Ⅰにより免責されないパターンとして、既に対象投稿について、裁判所がプロバイダに対し削除仮処分や削除判決を出し、かつ、プロバイダが特段不服申立て(保全異議や控訴)をしなかった場合が想定されます。
ただし、これらの裁判所の判断に基づき、合理的期間内に削除をすれば、少なくとも、不法行為に基づく損害賠償請求の要件のうち、①「故意又は過失」が否定され、結局損害賠償義務を負わないとされる可能性が高いと思われます。
Ⅱについて
Ⅱにより免責されないパターンとしては、個別の投稿について削除請求を受けて当該投稿の流通を知り、かつ、削除請求にあたり当該投稿が他人の権利を侵害すると判断できるだけの十分な根拠が提示された場合などが想定されます。
逆に、削除請求にあたり当該投稿が他人の権利を侵害することについて、十分な根拠が提示されず、プロバイダとして十分な事実調査をしないと判断できなかった場合は、原則通り免責ということになります。
例えば、名誉権侵害を理由とする削除請求を受けた際、当該請求では、当該投稿内容の真偽が分からないことを理由に削除しなかった場合については、免責される可能性が高いといえます。
請求を受けた場合の対応
以上のとおり、投稿を削除しなかったことに対する損害賠償請求が認められるためには、不法行為に基づく損害賠償請求の要件と、プロバイダ責任制限法上の免責にならない要件の両方を満たさなければならず、最終的に裁判所で認められるためのハードルは、相当程度高いものといえます。
このため、裁判外の請求であっても、裁判上の請求であっても、これらの要件のうち反論できる部分を検討し、安易に請求に応じないことが重要となります。
投稿を削除したことに対する損害賠償請求
投稿を削除したことに対する損害賠償請求としては、プロバイダと投稿者との間のサイト利用契約等を根拠とする債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条)が考えられます。
このような法律構成の場合、プロバイダは、契約違反といえなければ、損害賠償義務を負いません。
さらに、プロバイダ責任制限法3条2項は、プロバイダが損害賠償義務を負わない場合を2つ定めています。
投稿を削除しなかったことに対する損害賠償請求の場合(同法3条1項)と異なり、原則免責とはなっていませんので、注意が必要です。
債務不履行に基づく損害賠償請求の民法上の要件
民法415条に基づきシンプルに表現すると、
- 当該投稿を可能にする内容を含むサイト利用契約の締結
- ①の義務違反行為(削除行為)
- 「損害」が「生じた」こと
- ②と③の因果関係
- ②に過失がないとはいえないこと
が要件となります。
プロバイダとしては、投稿がサイト利用契約違反であること(②)、請求者側に投稿削除と因果関係のある損害が発生していないこと(③④)、投稿を削除したのもやむを得なかったこと(⑤)などの反論要素があります。
プロバイダ責任制限法3条2項の免責要件
プロバイダ責任制限法3条2項によれば、以下の2つのいずれかの場合であれば、プロバイダは免責されます。なお、細かい要件は他にもありますが、問題にならないことが多いため、ここでは割愛します。
- プロバイダが、情報(対象投稿)の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき
- プロバイダが、削除請求を受けた際、投稿者に対し、削除に同意するかどうか意見照会をしたにもかかわらず、7日を経過しても、投稿者から同意しない旨の回答がなかったとき
逆にいうと、Ⅰ又はⅡの場合以外は、他の要件を満たせば責任を負うということになります。
Ⅰについて
Ⅰにより免責されるパターンとして、削除請求がされ、その際、当該投稿が他人の権利を侵害すると判断できるだけの十分な根拠が提示されたため、削除に至った場合が想定されます。
Ⅱについて
Ⅱについては、免責の有無が形式的に判断できます。
こちらの免責に関しては、削除請求に対する普段の対応方針を決めるに当たって重要な規定です。
請求を受けた場合の対応
以上のとおり、投稿を削除したことに対する損害賠償請求については、債務不履行に基づく損害賠償請求の民法上の要件と、プロバイダ責任制限法上の免責要件に当たらないことの両方を満たさなければなりません。
削除請求対応にて、意見照会を活用した適切なフローを構築しておけば、請求を受ける可能性はかなり低いといえます。
請求を受けた場合であっても、裁判外の請求、裁判上の請求、いずれについても、これらの要件のうち反論できる部分を検討し、安易に請求に応じないことが重要となります。
発信者情報開示に関する損害賠償請求について
発信者情報開示に関する損害賠償請求については、開示請求者側からの開示しなかったことに対する損害賠償請求と、投稿者からの開示したことに対する損害賠償請求の2種類が考えられます。
プロバイダとしては、開示してもしなくても、これらのうちいずれかの損害賠償請求を受けるリスクがあります。
ただし、開示しなかったことに対する損害賠償請求についてはプロバイダ責任制限法上の免責規定があり、発信者情報開示請求権の要件が厳格であることもあり、プロバイダが過度に責任を負わない制度になっています。
以下、それぞれ、免責規定を中心に説明します
開示しなかったことに対する損害賠償請求
開示しなかったことに対する損害賠償請求は、民法709条、710条に定められた、一般的な不法行為に基づく請求です。
他方、プロバイダ責任制限法6条4項は、プロバイダが損害賠償義務を負う場合を故意又は重過失がある場合に限定し、これら以外の場合については(つまり、原則として)免責すると定めています。
開示しなかったことに対する損害賠償請求の要件
以上のような民法上の規定、プロバイダ責任制限法上の規定、判例(最三小判平22.4.13)などに照らすと、開示しなかったことに対する損害賠償請求の要件は、
- 開示請求があったのに開示しなかったこと
- 情報(対象投稿)の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなど当該開示請求がプロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求の要件を満たすことを認識し(故意)、又は、上記要件を満たすことが一見明白であり、その旨認識することができなかったことにつき重大な過失があること
- 「損害」が「生じた」こと
- ②と③の因果関係
が要件となります。
このうち、②の「故意」については、既に対象投稿について、裁判所がプロバイダに対し発信者情報開示仮処分や判決を出し、かつ、プロバイダが特段不服申立て(保全異議や控訴)をしなかったにもかかわらず開示しなかった(①)場合が想定されます。
また、②の「重大な過失」とは、「故意に近い注意欠如の状態」と解されています(総務省総合通信基盤局消費者行政第二課「プロバイダ責任制限法(第3版)」29頁(第一法規、2022年))。
「重大な過失」要件について
「重大な過失」が認められるためには、前提として、上記のとおり、
- プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求の要件を満たすことが一見明白であること
が必要とされています。
しかし、そもそも、発信者情報開示請求の要件は厳格です。特に、
- 情報(対象投稿)の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき
という厳しい要件があります(プロバイダ責任制限法5条1項1号)。
つまり、「重大な過失」が認められるには、「権利侵害が明らかであることが一見明白」であることが必要ということになります。
一回ざっと見るだけで権利侵害が明らかであることが明白であるような投稿は、ほとんど想定できません。例えば、判例(最三小判平22.4.13)では、「なにこのまともなスレ 気違いはどうみてもA学長」という投稿(本件書き込み)について、「本件書き込み中,被上告人を侮辱する文言は上記の「気違い」という表現の一語のみであり,特段の根拠を示すこともなく,本件書き込みをした者の意見ないし感想としてこれが述べられていることも考慮すれば,本件書き込みの文言それ自体から,これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが一見明白であるということはできず,本件スレッドの他の書き込みの内容,本件書き込みがされた経緯等を考慮しなければ,被上告人の権利侵害の明白性の有無を判断することはできないものというべきである。そのような判断は,裁判外において本件発信者情報の開示請求を受けた上告人にとって,必ずしも容易なものではないといわなければならない。」として、プロバイダが開示請求に応じなかったことについての「重大な過失」を否定しています。
プロバイダとしては、このような判例の判断に照らし、主に、「権利侵害が明らかであることが一見明白」とはいえないと反論することを検討すべきでしょう。
請求を受けた場合の対応
以上のとおり、開示しなかったことに対する損害賠償請求については、認容のハードルが極めて高いものといえます。
このため、裁判外の請求であっても、裁判上の請求であっても、反論可能な要素を検討し、安易に請求に応じないことが重要となります。
開示したことに対する損害賠償請求
開示したことに対する損害賠償請求は、民法709条、710条に定められた、一般的な不法行為に基づく請求です。
この場合、プロバイダの免責規定はありませんので、不法行為に基づく損害賠償請求の民法上の要件を満たせば、認容となってしまいます。
不法行為に基づく損害賠償請求の民法上の要件
民法709条によると、
- 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」したこと
- 「損害」が「生じた」こと、
- ①と②の因果関係
が要件となります。なお、これらの要件を満たした場合であっても、損害賠償義務を負わない場合があります(正当防衛など)。
プロバイダとしては、プロバイダ責任制限法上の発信者情報開示請求の要件を満たしていたこと、満たしていると判断してもやむを得なかったこと(いずれも①と考えられます。)、請求者側に投稿と因果関係のある損害が発生していないこと(②③)などの反論要素があります。
請求を受けた場合の対応
以上のとおり、開示したことに対する損害賠償請求については、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求の要件を満たせば認められてしまいます。
裁判外の請求であっても、裁判上の請求であっても、反論可能な要素を検討するのは、他の損害賠償請求と同様ですが、損害賠償請求が認められるリスクは、他と比較して高いといえます。
お気軽にお問い合わせください
以上のとおり、プロバイダはサイト上の投稿に関し、投稿者と権利侵害を主張する者との間で板挟みの立場であり、両者から損害賠償請求を受けるリスクを抱えています。
しかし、免責規定を踏まえた的確な反論により、損害賠償を免れられる可能性があります。
是非お気軽にお問い合わせください。